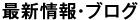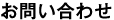- TOP>
- 最新情報・ブログ
2021年6月23日
【No.85樋口】油壷の戸建て
ゼントラストの樋口雄一です。
皆さんは油壷という地名をご存じですか?
神奈川県の三浦半島の南端にある三崎町という場所の近くにあります。
今日は油壷にある新築の戸建てを購入するお客様の仲介をしました。
もともとは京浜急行が所有していた一帯の土地を飯田産業が
開発した物件です。
都心の喧騒からはなれ、
統一されたきれいな色調の家が建ちならび、
海を近くに感じながらゆっくりとした時間が流れている場所です。

目の前にはヨットハーバー。

今回のコロナ禍を経験して「自分の時間を、どこで、どうすごしたいか」
住環境の大切さを改めて考えるきっかけになりました。
2021年5月31日
【No.84阿部】湿気対策
ゼントラストの阿部です。
今年は早い梅雨入りで驚きましたが、アジサイの花がきれいに咲いています。明日から6月になり学校などでは衣替えの時期でしょうか。企業などではクールビズが始まっていると思いますが、梅雨はやはり湿気が気になります。
住宅の中では、水回りや空気の通りが悪い場所にどうしてもカビが発生してしまいます。カビはアレルギーの原因にもなるので出来るだけ気を付けたいですね。
賃貸物件を探す時は、間取図で窓の大きさや位置、風が抜けるよう窓が複数あるかのチェックと、ベランダに洗濯物を干せるか、浴室乾燥機があるかなども確認しておくといいと思います。
北向きに部屋や収納がある場合は、内見の際に壁や中の状態もチェックしたいですね。オンライン内見で気になる部分のアップの映像を見せてくれるところもあるようです。
入居後は、家具を壁から少し離して置き、空気が流れるようにすることで湿気対策ができます。ベッドは湿気をもちやすいので、壁との間を空けるといいそうですよ。
除湿器やエアコンも使って少しでも過ごしやすい住まいにしたいものです。
2021年5月26日
【賃貸物件更新】マジェスタワー六本木503号室
ゼントラストの阿部です。
賃貸物件の情報を更新致しました。
【マジェスタワー六本木503号室】(詳細は下記をクリックしてください ⇓)
駅から近く共用設備も充実した物件です。
ご興味ありましたら、是非ゼントラストまでお問合せください。
2021年5月25日
【No.83渡邊】相続登記の義務化~2024年施行予定~
ゼントラストの渡邊です。
「所有者不明土地」の問題を解消するための民法・不動産登記法などの改正法が、本年4月21日可決、成立しました。
2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務付けられます。
今回の相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3つです。
1.相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
⇒相続で不動産取得を知った日から、または遺産分割の日から3年以内に登記
2.相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
⇒遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合に、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度が創設される
3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務付け(5年以内の施行)
⇒個人のほか、会社などの法人が住所変更した場合に2年以内に住所変更登記
相続登記と所有権の登記名義人の変更について、正当な理由がなく申請しなかった場合には、それぞれ過料を支払わないといけません。
法改正の背景には「所有者不明土地」の増加があります。
所有者不明土地とは、所有者は分かっても転居してしまっていて連絡先が分からないもの、土地の名義人が亡くなった後に相続登記がされないままで相続人が多くなり、全ての人に連絡するのが困難になったものなどを指します。
所有者が分からないと土地を売る事も、利用・活用することも難しく、所有者不明土地の増加は深刻な問題となっていました。
法律の施行まで時間があるものの、先回しにしてしまうと、さらに相続人が増えて手続きが複雑化する恐れもあります。
現時点で相続登記や住所変更登記をしていない場合には、速やかに、手続きされることをお勧めします。
私自身も変更登記をしていないので、折を見て手続きしたいと思います。
2021年5月25日
【賃貸物件更新】グレイシス西麻布402号室
ゼントラストの阿部です。
賃貸物件の情報を更新致しました。
【グレイシス西麻布402号室】(詳細は下記をクリックしてください ⇓)
設備充実のデザイナーズマンションです。
ご興味ありましたら、是非ゼントラストまでお問合せください。
新着記事
-
お知らせ 2025年09月25日
ビル改修工事に伴う一時移転のお知らせ -
物件情報 2025年09月18日
【賃貸物件更新】ライオンズマンション生麦南 608号室 <成約済> -
物件情報 2025年09月04日
【賃貸物件更新】ガリシアレジデンス目黒本町 405号室 -
物件情報 2025年09月01日
【賃貸物件更新】パレステュディオ飯田橋 405号室 <成約済> -
物件情報 2025年09月01日
【賃貸物件更新】マジェスタワー六本木603号室<成約済> -
ブログ 2025年10月02日
会社設立10周年 -
ブログ 2024年12月21日
日立シーサイドマラソン
カテゴリ
人気記事
- 2024年10月2日
会社設立9周年 - 2023年6月3日
ランニング - 2023年1月20日
物件情報をください! - 2023年12月2日
フルマラソン完走! - 2023年4月26日
読書
アーカイブ
- 10月
- 9月
- 8月
- 6月
- 5月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 10月
- 8月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 9月
- 8月
- 7月
- 5月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 2月
- 12月
- 9月
- 8月
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017