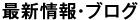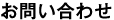- TOP>
- 最新情報・ブログ
2018年10月24日
【賃貸物件更新】月極駐車場久保寺パーキングⅡ
ゼントラストの鈴木です。
賃貸物件の更新を致しました。
【久保寺パーキングⅡ】(詳しくは下記をクリックしてください⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/■月極駐車場%e3%80%80西麻布久保寺パーキングⅡ/
西麻布の閑静な住宅街にあり、六本木通り、外苑西通りからも近く便利な立地です。
手前の広い区画を募集しておりますので、大型車の入庫も可能です!
ご興味がありましたら、是非ゼントラストまでお問合せください。
2018年10月16日
【賃貸物件更新】グランデール八王子
ゼントラストの鈴木です。
賃貸物件の情報を更新致しました。
【グランデール八王子】(詳細は下記をクリックしてください⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/■賃貸マンショングランデール八王子/
2016年3月にリフォームを実施しており、きれいなお部屋です。
また都心へのアクセスも良く、近くにスーパー・コンビニもありますので
生活にも大変便利な環境です!
ご興味がありましたら、是非ゼントラストまでお問合せください。
2018年9月26日
【賃貸物件更新】パレステュディオ飯田橋
ゼントラストの鈴木です。
賃貸物件の情報を更新致しました。
【パレステュディオ飯田橋】(詳細は下記をクリックしてください⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/【賃貸マンション】パレステュディオ飯田橋【ア/
5路線の利用可能な「飯田橋」駅徒歩6分!
目の前にスーパー「いなげや」があり毎日のお買い物も便利です。
また、お部屋も角部屋ですので二面採光で明るく開放的な空間です。
生活にお仕事に大変良好な環境です。
2018年9月6日
【賃貸物件更新】グランデール八王子
ゼントラストの鈴木です。
賃貸物件の情報を更新しました。
【グランデール八王子】(詳細は下記をクリックしてください ⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/■賃貸マンショングランデール八王子/
最寄りのバス停が目の前にあり、スーパーやコンビニも近くにありますので
生活に便利な環境です。
また、角部屋ですので二面採光で明るく開放的な空間が魅力です。
2018年9月3日
【賃貸物件更新】レ・ベント高円寺、パレステュディオ飯田橋
ゼントラストの鈴木です。
賃貸物件の情報を2件、更新しました。
【レ・ベント高円寺】(詳細は下記をクリックしてください⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/【賃貸マンション】レ・ベント高円寺【駅徒歩3分/
【パレステュディオ飯田橋】(詳細は下記をクリックしてください⇓)
https://www.zentrust.co.jp/service_info/【賃貸マンション】パレステュディオ飯田橋【ア/
2件とも駅近く、周辺環境も良く生活にお仕事に大変便利な環境です。
また、どちらも角部屋ですので日当たりが良く、開放感があるのも魅力です。
ご興味がありましたら、是非ゼントラストまでお問合せください。
新着記事
-
お知らせ 2025年09月25日
ビル改修工事に伴う一時移転のお知らせ -
物件情報 2025年09月18日
【賃貸物件更新】ライオンズマンション生麦南 608号室 <成約済> -
物件情報 2025年09月04日
【賃貸物件更新】ガリシアレジデンス目黒本町 405号室 -
物件情報 2025年09月01日
【賃貸物件更新】パレステュディオ飯田橋 405号室 <成約済> -
物件情報 2025年09月01日
【賃貸物件更新】マジェスタワー六本木603号室<成約済> -
ブログ 2025年10月02日
会社設立10周年 -
ブログ 2024年12月21日
日立シーサイドマラソン
カテゴリ
人気記事
- 2024年10月2日
会社設立9周年 - 2023年6月3日
ランニング - 2023年1月20日
物件情報をください! - 2023年12月2日
フルマラソン完走! - 2023年4月26日
読書
アーカイブ
- 10月
- 9月
- 8月
- 6月
- 5月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 10月
- 8月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 9月
- 8月
- 7月
- 5月
- 2月
- 1月
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 2月
- 12月
- 9月
- 8月
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017